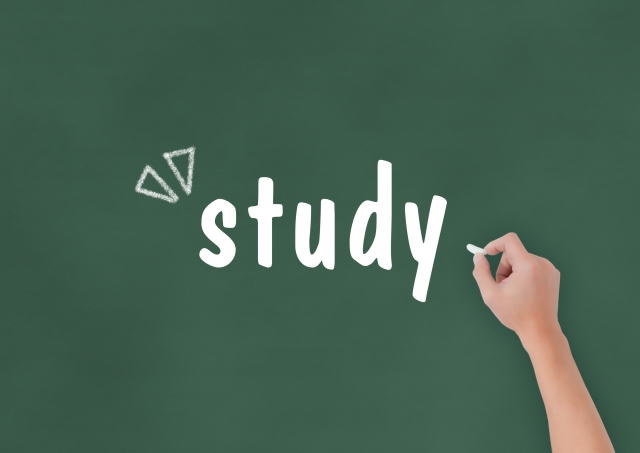国際医療福祉大学薬学部のオンライン授業を行いました。zoomを使って、途中で手揚げしてもらったりしながら、学生の反応をみています。講義室では手がなかなかあがらなくて、部屋を歩いて1人1人声かけしたりしますが、オンラインだと「手を挙げて」というとすぐ反応があるのが、新しい発見でした。慣れてくると、もっと良い授業ができる気がします。
新型コロナウイルス感染症の流行で大学の需要のうち、座学は、生徒皆が講義室に集まって授業をうける形では無く、(1)パワーポイントスライドに音声を録音してオンデマンドで動画配信する、(2)ズームを用いてライブ配信する、が主な方法になっているようです。大学によって異なるのですが、わたしはこの両方を行う機会を与えていただきました。
私がやってみた感想は、個人差もあるでしょうけど、やはりライブが良いと思いました。それは、語りかけて反応をみることもできるからです。また、ライブを録画しておけば、たとえば体調が悪くて出席できなかった学生に後日配信することも可能です。
スライドの説明を録音するのは、授業と言うよりも、資材として言い間違いのない完成度の高さが求められると思っています。また、臨場感がないので、90分はついていけない。自分でもyoutubeなどにあるハウツー的な動画は、30分あると飽きてきてしまいます。ある先生のお話ですと、スライドをあまりに沢山用意して配信すると学生から不満が多いとのことです。授業時間が90分だからスライドも90分しっかり勉強を、と学生の勉強のためを想ってのことかと思います。受ける側と提供する側、双方の最大公約数での授業ができれば良いなと思いました。
オンラインのみだった大学の授業は、半数の学生を大学で受講、残りの半数は自宅でオンライン、という組み合わせ方式も行われています。ただ、講師である私の方が、県境を越えた大学への異動を控える状況でしたので、全員自宅に戻ってもらってオンライン配信でした。
今後の大学の授業は、講義室の授業も含め動画配信を併用しながら、地域に関係なく大学で指導を受けることがより普及すると思います。そうなりますと、地方にあっても優秀な大学が生き残ることができます。逆に、東京にあるから、都心にあるから、という地の利は、これから学生とくに社会人学生にとってのアピールポイントではなくなると想います。
地方の大学でも、オンラインで充実した授業を提供して、オンラインと活用して学生を指導する、
私が10年前 2008年〜20011年に英国リバプール大学にてオンラインで学習したときのようなことが、もっと日本でも普及するようになると思います。